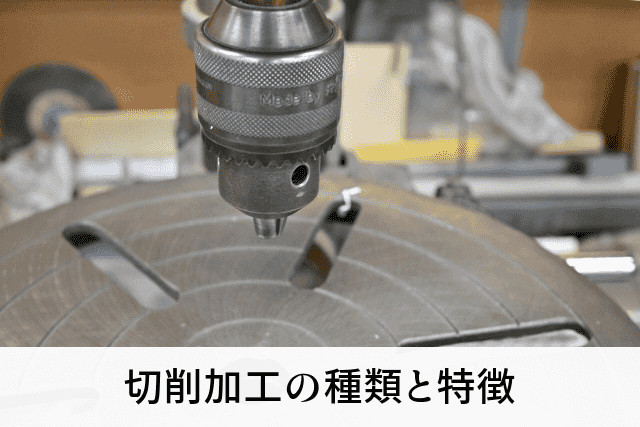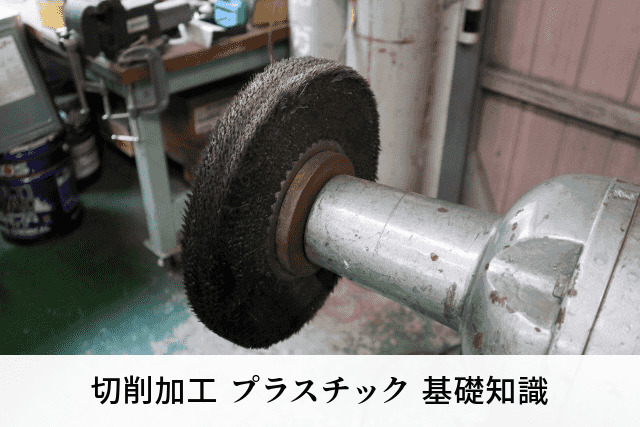旋盤加工と切削加工の違い
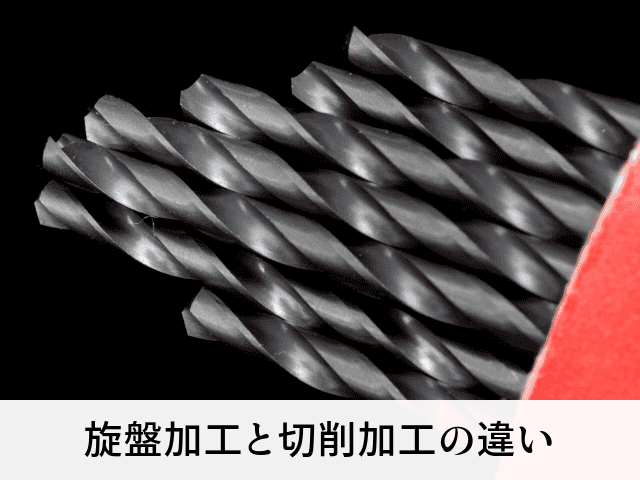
旋盤加工とは?ターニングの基本と特徴

旋盤加工(ターニング)は、切削加工の一種であり、材料を回転させながら固定された切削工具を押し当てて削る加工方法です。この加工法は主に円柱形状の部品製作に適しており、シャフトやボルト、パイプなどの製造によく用いられます。
旋盤加工の最大の特徴は、材料が回転し続ける間、切削工具(バイト)が常に材料に接触し続ける「連続切削」という点です。これにより、リンゴの皮を剥くように連続的な線状の切りくずが発生します。
旋盤加工で使用される主な工具はバイトと呼ばれ、その構造によって以下のように分類されます:
- ムクバイト:刃先とシャンクが同じ素材で一体となっているもの
- 付刃バイト:刃先をシャンクに溶着しているもの
- スローアウェイバイト:シャンクの先端に刃先(チップ)を取り付け、摩耗時に交換可能なもの
また、形状によっても以下のように分類されます:
- 片刃バイト:シャンクの左右どちらかにのみ刃が付いている
- 剣バイト:刃先が剣のように尖っている
- 突っ切りバイト:外周の溝入れや切断に使用
- ねじ切りバイト:ねじ山を作る際に使用
- 中ぐりバイト:内径を切削する
近年では、コンピュータ制御により自動で加工を行うCNC旋盤(NC旋盤)が主流となっており、複雑な形状でも高精度な加工が可能になっています。
切削加工の種類と旋盤加工の位置づけ
切削加工とは、工具を用いて金属などの材料を削ったり穴を開けたりする加工の総称です。基本的には旋盤やフライス盤、マシニングセンタ、ボール盤などの工作機械を使用し、刃物状の工具を使って工作物の不要部分を除去することで必要な形状を作り出します。
切削加工は大きく分けると以下のような種類があります:
- 旋削加工(旋盤加工・ターニング)
- 材料を回転させ、固定した工具で削る
- 円柱形状の加工に適している
- フライス加工(ミーリング)
- 工具を回転させ、固定した材料を削る
- 平面や角物の加工に適している
- 穴あけ加工(ドリル加工)
- 回転するドリルで材料に穴を開ける
- 研削加工
- 砥石を用いて材料表面を削る
- 高精度な仕上げに使用される
これらの中で、旋盤加工は切削加工の一種として位置づけられています。切削加工全体の中では、円柱形状の加工に特化した方法として重要な役割を担っています。
切削加工全般のメリットとしては、様々な硬度の材料に対応できること、精度の自由度が高いこと、初期コストが低いことなどが挙げられます。一方、デメリットとしては、大量生産には不向きであること、切りくずが発生して歩留まりが悪化することなどがあります。
旋盤加工とフライス加工の違いを徹底比較
旋盤加工とフライス加工は、どちらも切削加工の代表的な方法ですが、いくつかの重要な違いがあります。以下に両者の主な違いを比較します。
1. 加工方法の違い
| 旋盤加工 | フライス加工 |
|---|---|
| 材料(ワーク)を回転させる | 切削工具を回転させる |
| 切削工具は固定されている | 材料(ワーク)は固定されている |
| 連続切削(工具が常に材料に接触) | 断続切削(工具と材料の接触と非接触を繰り返す) |
| 切りくずは連続的な線状 | 切りくずは分断されたチップ状 |
2. 使用する工具の違い
| 旋盤加工 | フライス加工 |
|---|---|
| バイト(片刃バイト、剣バイト、突っ切りバイト等) | フライス工具(正面フライス、平フライス、溝フライス等)、エンドミル |
| 工具に求められる特性:耐摩耗性が重要 | 工具に求められる特性:衝撃に対する粘り強さ、耐熱衝撃性が重要 |
3. 加工に適した形状の違い
| 旋盤加工 | フライス加工 |
|---|---|
| 円柱形状の加工に適している | 平面や角物の加工に適している |
| シャフト、ボルト、ピン、ブッシュ等の製作に向いている | 平面加工、溝加工、ポケット加工等に向いている |
| 真円度の高い加工が可能 | 複雑な形状の加工が可能 |
| 内径が小さく深い加工に適している | 外径が大きい加工に適している |
4. 加工精度と仕上がりの違い
旋盤加工は真円度の高い加工を実現でき、エネルギーロスや加工不良が起こりにくいという特徴があります。一方、フライス加工は仕上がりが綺麗で不良品が少なく、特に寸法精度が必要な精密部品加工に適しています。
5. 切りくずの形状の違い
旋盤加工では連続的な線状の切りくずが発生するため、切りくずの処理が課題となることがあります。一方、フライス加工では断続的なチップ状の切りくずが発生するため、比較的処理がしやすいという特徴があります。
両加工方法の特性を理解し、加工する部品の形状や要求される精度に応じて適切な加工方法を選択することが重要です。
旋盤加工の切りくずから分かる加工状態
旋盤加工において、切りくず(切粉、ダライ粉とも呼ばれる)は加工状態を知る上で非常に重要な情報源です。切りくずの色、形状、長さなどを観察することで、切削条件や刃物の状態が適切かどうかを判断することができます。
1. 切りくずの色からわかること
旋盤加工では材料と刃物の間に高熱が発生します。この熱により切りくずの表面に酸化被膜が形成され、その厚みによって様々な色(干渉色・テンパーカラー)に見えるようになります。
- 青色や虹色の切りくず:高温での切削を示し、刃物の寿命を縮める可能性がある
- 金色や茶色の切りくず:適切な温度での切削を示す
- 材料本来の色に近い切りくず:低温での切削を示す
切削油や冷却水を使用するウェット加工では、この色の変化は起きにくくなります。
2. 切りくずの形状からわかること
JIS(日本産業規格)では、切りくずの形状を以下の4パターンに分類しています:
- 流れ形:切削条件のバランスや刃物の状態が良く、安定した状態を示す
- せん断形:切削に少し変動があり、加工精度がやや落ちる状態を示す
- き裂形:材質がもろい場合に発生し、加工精度が良くない状態を示す
- むしれ形:切りくずがうまく排出されておらず、加工精度が良くない状態を示す
特に「むしれ形」の切りくずが発生する場合、「構成刃先」と呼ばれる現象が起きている可能性があります。これは材料の一部が刃先に付着して切削を妨げる現象で、刃物の材質変更や切削条件の調整などで対処します。
3. 切りくずの長さや巻き数からわかること
切りくずの長さと巻き数も重要な情報です:
- 長い螺旋状の切りくず:材料や機械に巻き付く危険があり、作業効率が下がる
- 適度な長さの螺旋状切りくず:一般的に好ましく、切削が安定している状態を示す
- 短いチップ状の切りくず:切削が不安定な状態を示す可能性がある
長い切りくずが問題となる場合は、チップブレーカー付きの刃物や揺動切削システムを使用することで対処できます。
切りくずを定期的に観察することで、加工している金属材料の種類、刃物の選択や切削条件の適切さ、加工精度の状態、刃物の摩耗具合などを判断することができます。これにより、加工品質の向上や工具寿命の延長につながります。
旋盤加工の工程短縮と効率化のポイント
旋盤加工の効率化は、製造コストの削減や納期短縮に直結する重要な課題です。ここでは、旋盤加工の工程短縮と効率化のためのポイントを解説します。
1. 適切な切削条件の設定
切削速度、送り量、切り込み量の3要素を適切に設定することが重要です。
- 切削速度:材料や工具に応じた最適な速度を選択する
- 送り量:大きすぎると工具寿命が短くなり、小さすぎると加工時間が長くなる
- 切り込み量:大きすぎると工具に負担がかかり、小さすぎると効率が下がる
これらのバランスを取ることで、加工時間の短縮と工具寿命の延長を両立できます。
2. 工具選択の最適化
加工内容に最適な工具を選択することで、効率が大きく向上します。
- スローアウェイバイトの活用:チップ交換だけで済むため、段取り時間を短縮できる
- 複合工具の使用:一つの工具で複数の加工ができるため、工具交換回数を減らせる
- コーティング工具の選択:耐摩耗性が向上し、高速切削が可能になる
3. 複合加工機の活用
現代の旋盤加工では、複合加工機の活用が効率化の鍵となります。
- 複合旋盤:旋削だけでなく、フライス加工や穴あけ加工も1台で可能
- 自動工具交換機能:工具交換時間を大幅に短縮
- 多軸制御:複雑な形状も一度の段取りで加工可能
4. プログラミングの最適化
CNC旋盤を使用する場合、加工プログラムの最適化が重要です。
- 効率的な工具経路の設定:無駄な動きを減らし、加工時間を短縮
- 適切な加減速制御:機械の特性を考慮した加減速で、サイクルタイムを短縮
- シミュレーションの活用:実際の加工前に問題点を発見し、修正
5. 段取りの効率化
加工時間だけでなく、段取り時間の短縮も重要です。
- 段取り替え時間の短縮:治具の標準化やクイックチェンジシステムの導入
- ワンタッチ段取り:工具やワークの位置決めを簡素化
- 段取り作業の標準化:作業手順を明確にし、ムダを排除
6. VA・VE提案の活用
製品設計段階からの見直しも効率化に貢献します。
- R形状の追加によるコストダウン:直角部分にRを付けることで、小径工具での加工を避け、加工時間を短縮
- 加工しやすい形状への変更提案:設計変更により加工工程を簡略化
これらのポイントを総合的に検討し、自社の加工内容や設備に合わせた最適な方法を選択することで、旋盤加工の工程短縮と効率化を実現できます。また、定期的な見直しと改善を続けることで、さらなる効率化が期待できます。
金属加工を依頼する際の旋盤加工と切削加工の選び方
金属加工を外部に依頼する際、旋盤加工と他の切削加工のどちらを選ぶべきか悩むことがあります。ここでは、加工方法を選択する際のポイントを解説します。
1. 製品形状による選択
製品の形状は加工方法を決める最も重要な要素です。
- 円柱形状の部品(シャフト、ピン、ブッシュなど)→ 旋盤加工が適している
- 平面や角物の部品(ブロック、プレートなど)→ フライス加工が適している
- 内径が小さく深い穴がある部品 → 旋盤加工が適している
- 外径が大きい部品 → フライス加工が適している
2. 要求精度による選択
要求される精度によっても最適な加工方法は異なります。
- 真円度が重要な場合 → 旋盤加工が適している
- 平面度や直角度が重要な場合 → フライス加工が適している
- 超高精度が必要な場合 → 加工後に研削加工を追加することも検討
3. 材料特性による選択
加工する材料の特性も考慮する必要があります。
- 延性材料(アルミニウム、ステンレス、銅合金など)→ 切りくずが長くなりやすいため、**チップブレーカー付きの