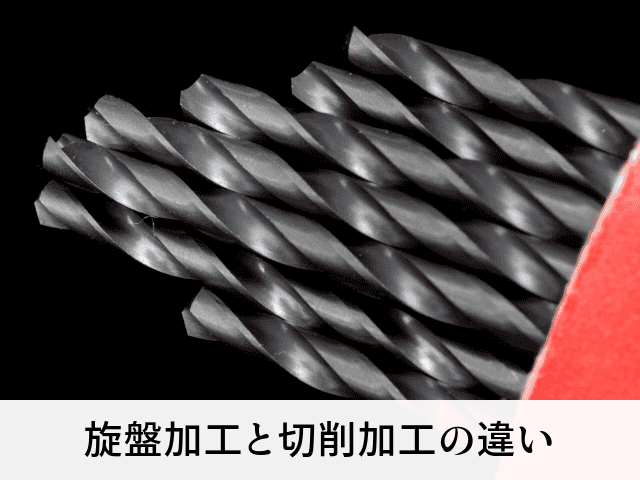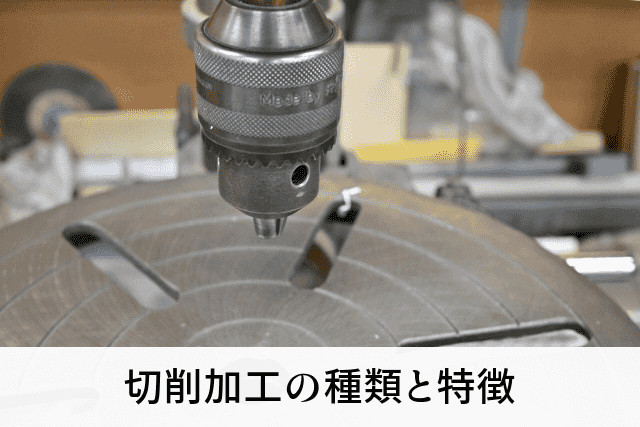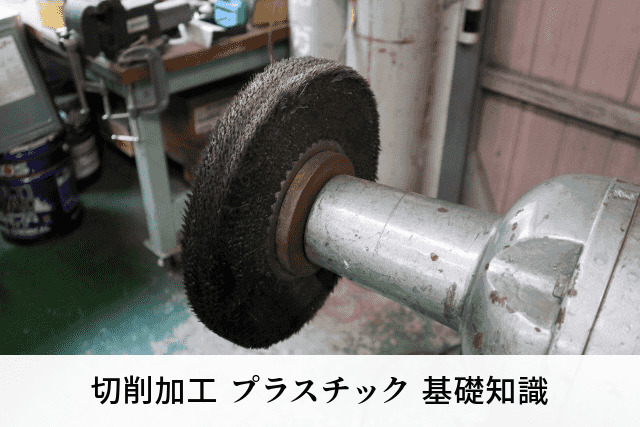真鍮加工の特性と方法
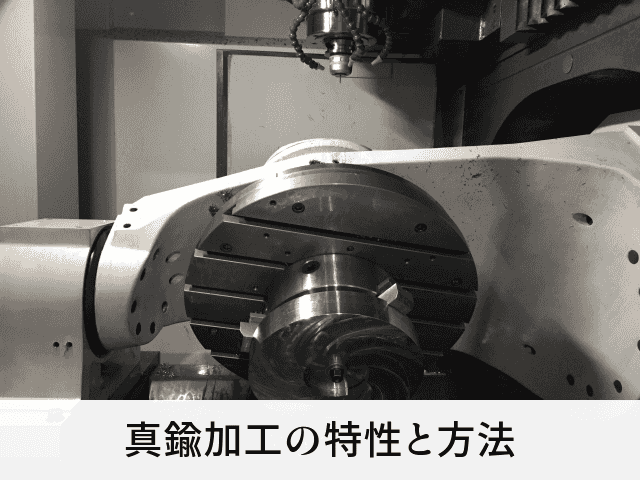
真鍮(しんちゅう)は銅(Cu)と亜鉛(Zn)を主成分とする合金で、その美しい金色の輝きから黄銅(おうどう、こうどう)とも呼ばれています。身近なものでは5円玉やトランペットなどの金管楽器、アクセサリーなどに使用されている金属素材です。
真鍮は他の金属素材と比較してコストが比較的安く、切断・曲げ・切削・溶接など様々な加工方法に対応できる点が大きな魅力です。しかし、その特性ゆえに加工が難しいとされる側面もあります。本記事では、真鍮の特性や加工方法、加工時の注意点について詳しく解説していきます。
真鍮の基本特性と亜鉛含有量による違い
真鍮は銅に亜鉛を添加した合金で、亜鉛の含有量によって特性が大きく変わります。亜鉛含有量が30%までのものはα黄銅と呼ばれ、軟らかさがあるため加工性に優れています。一方、亜鉛含有量が40%を超えると(α+β)黄銅となり、硬さと機械的強度が増し、色合いも黄金色に近い黄色になります。
真鍮の主な特性は以下の5つです:
- 展延性が高い:常温で伸ばしても破損しないため、細い線や薄板への加工に適しています。
- 切削性が高い:被削性を高める亜鉛が添加されているため、精密加工が必要な機械部品の材料に適しています。
- 耐食性が高い:表面は酸化しやすいものの、内部まで腐食されにくいという特徴があります。
- 電気伝導性が高い:電気を通しやすい特性を持っています。
- 熱間鍛造性が高い:熱を加えることで多種多様な形状に加工しやすい特性があります。
亜鉛含有量による特性の違いは以下の表のようにまとめられます:
| 名称 | 銅 | 亜鉛 | 加工性 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| α黄銅 | 70% | 30% | 軟らかく、高温加工に適さない。常温加工と中間焼きなましを実施 | 金管楽器など |
| (α+β)黄銅 | 60% | 40% | 硬く、高温加工が可能。600~800℃で一次加工、常温で二次加工を実施 | 配線器具など |
真鍮の切削加工におけるフライス加工と旋削加工の違い
真鍮の切削加工には主に「フライス加工」と「旋削加工」の2つの工法が用いられます。
フライス加工は、固定した真鍮に対して機械に取り付けた工具を回転させて切削する方法です。ドリルやエンドミルなどの回転工具を用いて、穴あけや平面加工、溝加工などを行います。複雑な形状の加工に適しており、±0.1mmや±0.01mmといった高精度の加工が可能です。
旋削加工(旋盤加工)は、真鍮自体を回転させ、工具を当てて切削する方法です。主に円筒形状の加工に適しており、外径の切削や内径の加工、ねじ切りなどを行うことができます。
切削加工の大きなメリットは、金型などを使わないためイニシャルコストが低く済む点です。一方、1製品当たりの単価は高くなる傾向があります。
切削加工を行う上で重要な注意点は以下の2つです:
- 切削熱による変形:真鍮は熱伝導率が高いため、切削時に発生する熱によって変形が生じやすくなります。
- バリの発生:真鍮は展延性に優れているため、切削加工時にバリが発生しやすいという難点があります。
これらの問題を防ぐためには、加工条件を低めに設定したり、油性の切削油を十分にかけたりするなどの対策が必要です。また、適切かつ良質な工具の選定や、クーラント(冷却材)を用いて摩擦熱による変形や溶着を防ぎ、バリの原因となる削り残しをなくすことも重要です。
真鍮の曲げ加工と冷間加工・熱間加工の使い分け
真鍮の曲げ加工では、その優れた展延性により「冷間加工」と「熱間加工」の2通りの方法を選択できます。それぞれの特徴と適性は以下の通りです:
冷間加工は、塑性変形を利用し、常温から再結晶温度未満で行う加工方法です。大きめのRに曲げるなど比較的簡単な形状の加工に適しています。常温での加工により、金属の変形抵抗が保たれるため、形状や精度が損なわれにくいという利点があります。
熱間加工は、再結晶温度以上に加熱し、金属の変形抵抗を下げることで金属の変形能力を高める加工方法です。小さめのRや波曲線のような複雑な形状の加工に適しています。変形抵抗が大幅に下がっているため加工がしやすいという特徴があります。
曲げ加工には、プレスブレーキ加工やプレス加工などの方法があります:
- プレスブレーキ加工:汎用的な金型を用いて薄板を曲げる方法で、イニシャルコストがかからないため中小ロットでの加工に適しています。
- プレス加工:専用の金型を作成する必要がありますが、加工速度が早く、切断加工と同時に曲げができる場合もあり、量産性に優れています。
曲げ加工を施すことで、材料に強度を持たせることが可能になります。ただし、真鍮の特性上、熱による反りが生じやすいため、加工条件の設定には注意が必要です。
真鍮の溶接加工とロウ付け接合の技術的ポイント
真鍮の溶接には主に「抵抗溶接」と「ロウ付け接合」の2つの工法があります。
抵抗溶接は、局部的に短時間で溶接を行う工法で、溶接熱による部材への熱影響が少ないという特徴があります。抵抗溶接には以下のような種類があります:
- 抵抗スポット溶接
- プロジェクション溶接
- バット溶接
- 抵抗シーム溶接
- 抵抗スタッド溶接
このうち、真鍮の溶接に向いているのは「抵抗スポット溶接」と「プロジェクション溶接」です。抵抗スポット溶接は抵抗溶接の中でもポピュラーな工法で、プロジェクション溶接は溶接後の負荷(熱歪等)を最小限に抑えるため、厚板の接合にも適しています。
ロウ付け接合は、部品の接合方法の一種で、接合する部品をガスバーナー等で加熱し、加熱部に近づけ溶かしたロウ材を部材間に流し込み冷却して接合する工法です。
真鍮は熱伝導率が高いという特性があり、これが溶接時に問題となる場合があります。熱が真鍮自体に拡散しやすく、融合不良や溶接時に発生する金属のカス(スラグ)巻き込みといった欠陥につながりやすいためです。
これらの不具合を防止するためには、十分な予熱が必要になります。また、冷却時の割れなど真鍮の溶接では注意すべき点が多く、対策としてロウ付け接合が用いられることが多いです。
真鍮は熱伝導率が非常に高いため、基材を溶かして加工すると本体を溶かしてしまう場合があります。そのため、真鍮の溶接には高い技術が必要です。このような熱伝導率の問題があるため、真鍮を溶接する場合は、真鍮よりも低い温度で溶ける銀ロウを使った「ロウ付け」がよく利用されます。
真鍮の鏡面加工技術と仕上がりの美しさを左右する要素
鏡面加工とは切削後に行う後処理の一つで、表面を研磨して鏡のように滑らかに仕上げる加工方法です。鏡面研磨やミラー仕上げとも呼ばれます。この加工は、切削加工後に生じたバリを取り除くことができるほか、加工品の安全性を高めることも可能です。
真鍮の鏡面加工には主に以下の3つの方法があります:
- バフ研磨:綿やフェルトで作られたバフを高速回転させ、研磨剤を塗布しながら研磨する方法です。職人による手作業で行われるため、仕上がりが美しいというメリットがありますが、手作業のため仕上がりに差があり、大量ロットの生産が難しいというデメリットがあります。
- バレル研磨(機械):タンク型の機械を使用し、中に研磨させる素材と研磨石や研磨剤・水を入れて研磨する方法です。機械研磨のため、バフ研磨に比べて大量ロットの生産が可能ですが、部分的な研磨ができないというデメリットがあります。
- 電解研磨:素材を電解研磨液に浸し、電気を用いて化学反応で金属表面を変化させて研磨する方法です。表面を均一に加工でき、細かい部分など研磨しづらい箇所も可能というメリットがありますが、素材1つ1つに装置を取り付ける必要があり、コストがかかるというデメリットがあります。
真鍮は研磨することで、金に近い美しい色味を出すことができます。金に比べて価格が圧倒的に安いため、金のゴージャス感を出したい製品には最適な素材です。ただし、真鍮は表面が酸化しやすく、時間が経つと黒ずんでくるという特性があります。そのため、真鍮の美しい色味を長く保ちたい場合は、クリアコートを施すなどの表面処理が必要です。
真鍮の鏡面加工の仕上がりを左右する要素としては、以下のようなものが挙げられます:
- 研磨前の表面状態(傷や凹凸の有無)
- 研磨剤の種類と粒度
- 研磨時間と圧力
- 職人の技術と経験
特に職人の技術は重要で、同じ方法でも職人によって仕上がりに差が出ることがあります。そのため、真鍮の鏡面加工を依頼する際は、実績のある信頼できる業者を選ぶことが重要です。
真鍮加工は、その特性を理解し適切な方法で行うことで、美しく機能的な製品を生み出すことができます。加工方法によって仕上がりや特性が異なるため、製品の用途や求められる品質に合わせて最適な加工方法を選択することが大切です。
真鍮は加工性に優れた素材ですが、その特性ゆえに加工が難しいとされる側面もあります。そのため、真鍮の加工を依頼する際は、実績と熟練の技術を持つ職人が在籍する業者を選ぶことが重要です。適切な加工方法と技術によって、真鍮の持つ美しさと機能性を最大限に引き出した製品を作り出すことができるでしょう。