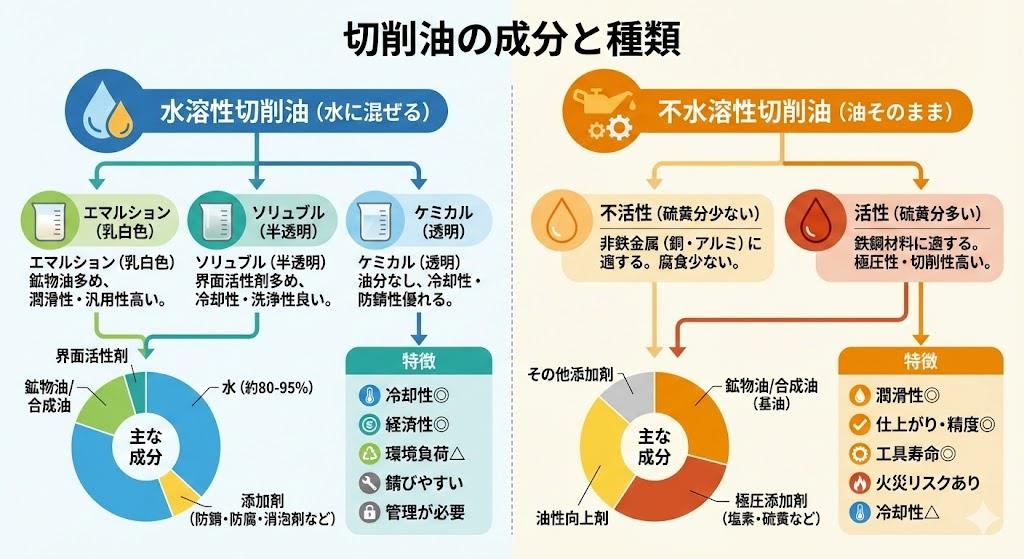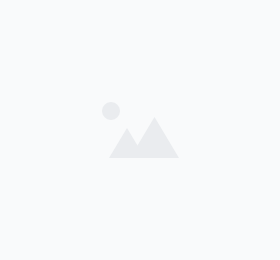大同特殊鋼の加工方法と特殊鋼材の活用技術
大同特殊鋼の工具鋼における熱間加工技術の最新動向
大同特殊鋼の工具鋼は、熱間加工における高い性能を発揮するよう設計されています。特にホットスタンピング向けに開発された「DHA-HS1」は、業界トップレベルの高熱伝導率を実現した画期的な金型用鋼です。この素材は、高温に加熱した鋼板をプレス成形する工程で使用され、熱伝導率の高さから金型の冷却時間を大幅に短縮できます。
ホットスタンピング加工では、金型の温度管理が製品品質と生産効率に直結します。DHA-HS1は従来の金型材料と比較して熱の拡散性に優れているため、金型内の温度ムラを抑制し、成形品の寸法精度向上にも貢献します。さらに、軟化抵抗が高いという特性により、高温環境下でも金型の硬度低下を防ぎ、金型寿命の延長を実現しています。
熱間加工における金型の冷却は、単に生産サイクルタイムを短縮するだけでなく、成形される部品の金属組織や機械的特性にも影響を与えます。DHA-HS1を使用した金型では、効率的な冷却により、成形品の強度や硬度を精密にコントロールすることが可能になりました。
大同特殊鋼では、実際の加工環境を模擬したテスト設備を導入し、サーボプレス、加熱炉、ロボットを配置したホットスタンピング設備で材料特性や金型温度が金型損傷に及ぼす影響を継続的に研究しています。この研究開発体制により、より高度な熱間加工技術の開発が進められています。
大同特殊鋼の金型材料におけるダイカスト加工の最適化手法
ダイカスト加工は、溶融金属を高圧で金型に射出して精密な部品を製造する技術ですが、金型材料には高い耐熱性と耐摩耗性が求められます。大同特殊鋼では、ダイカスト金型向けに特化した熱間工具鋼を開発し、加工プロセスの最適化に貢献しています。
大同特殊鋼の熱間工具鋼シリーズには、大型金型に適した高焼入れ性鋼「DHA-WORLD」や「DH31-EX」、そして高熱伝導率鋼「DHA-Thermo」があります。これらの材料は、ダイカスト加工時の過酷な熱サイクルや溶融金属との接触による損傷に対して高い耐性を持っています。
ダイカスト金型の性能評価には、小型ダイカストマシンやヒートチェック試験機、溶損試験などが活用されています。これらの試験により、材料特性が金型損傷に及ぼす影響を詳細に分析し、最適な金型材料の選定や加工条件の設定が可能になります。
金型の表面処理技術も重要な要素です。大同特殊鋼では、溶接棒「DHW」や窒化などの表面処理技術を開発し、金型の耐久性向上を実現しています。これらの技術を組み合わせることで、ダイカスト加工の効率化と製品品質の向上が図られています。
最近では、ギガキャストと呼ばれる大型ダイカスト技術や新しいアルミ合金への対応も進められており、自動車産業などの高度な要求に応える金型材料の開発が続けられています。
大同特殊鋼の構造用鋼における浸炭熱処理と加工硬化の関係性
構造用鋼の性能を最大限に引き出すためには、適切な熱処理が不可欠です。大同特殊鋼では、e-Axle用高強度歯車用鋼など、電動車向けの高性能構造用鋼を開発しています。これらの鋼材は、浸炭処理と加工硬化を組み合わせることで優れた機械的特性を実現しています。
真空浸炭用鋼「DEGシリーズ」は、大同特殊鋼の真空浸炭炉「モジュールサーモ」とショットピーニング(SP)技術を組み合わせることで、従来材と比較して約2倍の疲労強度を達成しています。この高い疲労強度は、e-Axleなどの電動駆動系部品の小型軽量化と長寿命化に大きく貢献しています。
浸炭熱処理の温度と時間は、鋼材の特性に大きな影響を与えます。高温浸炭は処理時間の短縮に寄与しますが、結晶粒の粗大化という問題があります。大同特殊鋼の「ATOM鋼」は、高温浸炭でも結晶粒粗大化を抑制できる特性を持ち、省エネルギー化とカーボンニュートラルに貢献しています。
加工硬化と熱処理の組み合わせも重要な技術です。JISでは、アルミ合金の展伸材における加工硬化の程度を「H」記号で表し、H1は加工硬化のみを行ったもの、H2は加工硬化させたものに軟化熱処理したもの、H3は加工硬化の後に安定化処理したものを示します。これらの処理方法は、最終製品の硬度や強度、耐久性に大きく影響します。
大同特殊鋼の「DSGB鋼」は高い衝撃強度と優れた冷間鍛造性を兼ね備えており、歯車の小型軽量化に貢献しています。また、「ALFA鋼/S-ALFA鋼」や高周波焼入れ用「HAC鋼」は、冷間鍛造前の軟化熱処理を省略できる特性を持ち、製造プロセスの効率化とCO2排出削減に寄与しています。
大同特殊鋼の3Dプリンタ用金属粉末による革新的な金型加工法
金属3Dプリンティング技術の進化により、従来の切削加工では困難だった複雑な形状の金型製作が可能になっています。大同特殊鋼は、この革新的な加工技術に対応した3Dプリンタ用金属粉末を開発し、金型製造の新たな可能性を切り開いています。
大同特殊鋼が開発した「HTCシリーズ」は、SKD61相当の特性を持つ金属3Dプリンタ用粉末材料です。従来のマルエージング鋼粉末は造形性に優れるものの、造形したままでは35HRC程度の硬さにしかならず、40HRC以上で使用するダイカスト金型には硬度が不足していました。一方、SKD61相当材の粉末は造形したままで50HRCを超える硬さが得られますが、造形が難しいという課題がありました。
HTCシリーズでは、この相反する要素をバランスよく両立させるため、炭素添加量を最適化しています。これにより、造形したままで40〜45HRCの硬さを確保しつつ、造形性を改善することに成功しました。さらに、造形後の焼き戻しで50HRCまでの硬さ調整が可能になり、用途に応じた柔軟な対応が可能になっています。
HTCシリーズのもう一つの大きな特長は、高い熱伝導性です。マルエージング鋼と比較して2倍、従来のSKD61と比較しても1.5倍の熱伝導率を実現しています。この高い熱伝導性により、金型内に自由に水冷管を配置することが可能になり、効率的な冷却と型寿命の延長を両立できるようになりました。
金属3D造形における課題としては、造形時の割れ防止が挙げられます。大同特殊鋼では、割れの起点となる鋭い角を作らないデザインの採用や、造形後にショットブラストなどで造形面を平滑化することを推奨しています。また、現状では150mm角以上のサイズを造形すると割れが生じやすくなるため、大型金型への適用にはさらなる技術開発が進められています。
大同特殊鋼のステンレス鋼における耐水素特性と冷間加工の最新技術
水素社会の到来に向けて、水素環境下で使用される金属材料の開発が急速に進んでいます。大同特殊鋼は、水素ガス環境中で鋼材が脆くなる「水素脆化」という現象に対応するため、耐水素脆性と高強度を両立したステンレス鋼「DSN® 9-H2」を開発しました。
水素脆化は、水素原子が金属結晶格子内に侵入し、材料の延性や靭性を低下させる現象です。従来、水素環境下で使用される鋼材は低強度なものに限られていましたが、DSN® 9-H2の開発により、FCV(燃料電池自動車)部品や水素ステーション部品の小型化・軽量化が可能になりました。
ステンレス鋼の冷間加工技術も進化しています。冷間加工は、室温で金属に塑性変形を与える加工法で、高い寸法精度と表面品質が得られる利点があります。JISでは、アルミ合金の冷間加工硬化の程度をH1n(nは1〜9の数字)で表し、例えばH11は「1/8硬質になるよう加工硬化のみを行ったアルミ合金の展伸材」を意味します。
大同特殊鋼では、冷間工具鋼の分野でも成分設計や製造工程による組織制御の研究を進め、高硬度・高靭性冷間ダイス鋼「DCMX」を開発しました。この材料は、ハイテン鋼板を順送金型で加工する際の金型寿命を大幅に向上させる特性を持っています。
さらに、PVDコーティング技術の開発も進められており、1.2GPaから1.5GPaの超ハイテン鋼板を加工する金型への適用が研究されています。これらの技術開発により、自動車産業などで進む軽量化と高強度化の両立に貢献しています。
大同特殊鋼の特殊鋼材と加工技術は、金属加工業界の技術革新を支える重要な要素となっています。熱間加工、冷間加工、3D造形など様々な加工方法に対応した材料開発により、より高性能で効率的な金属部品の製造が可能になっています。今後も、カーボンニュートラルや水素社会などの社会的要請に応える新たな特殊鋼材と加工技術の開発が期待されています。